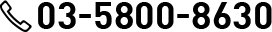老年病科
老年病科は、内科診療部門の1領域として、高齢者の総合診療を行っております。主として、65歳以上の患者さんを対象として、多様な疾患に対し、外来診療および入院診療を提供しています。認知症、フレイル(要介護状態の前段階)・サルコペニア(加齢に伴う筋肉量や筋力の低下)などの加齢に伴う病気、食欲低下・体重減少などのように原因がわかりにくく、どこの診療科へ行けばよいか分からない症状を有する場合、複数の臓器にまたがる複数の疾患をお持ちで臓器別の診療では診療先が決定しない患者さんなどを老年病科は診療の対象としています。骨粗鬆症のように、病気そのものの症状はないが、転倒・骨折を介して要介護状態に至る危険のある病気を予防的に対処する取り組みも行っております。また、当科の特徴として、救急診療の割合が高いことが挙げられます。高齢者は、一つの病気から多くの臓器の障害に至ることが多く、ささいな体調不良から救急診療に至る事例が多いと考えられます。当科では、多くの緊急入院の患者さんを診療しております。
高齢者の特徴として、一人の患者さんが多くの病気と症状を抱えていることあげられます。当科では、複数の病気により引き起こされる老年症候群と呼ばれる高齢者に多い症候・症状にも専門的知識を結集して診療にあたっています。さらには生活機能、認知機能、精神状態など多面的な尺度から患者さんを評価する高齢者総合的機能評価(CGA)を積極的に活用し、高齢者を個人として包括的に診療することで、「病気を治す」だけではなく、ADLやQOLを重視し「病人をよくする」ことを目標としています。高齢者は、多様な病気を持ち、人生経験も多様であるため、治療やケアの目標設定には、患者さんの価値観を理解することが重要となります。当科では、通常の診療時より、患者さんの望みを把握するようにしており、さらにご自身で意思決定ができなくなる状況にそなえて予めご本人やご家族と話し合うアドバンス・ケア・プラニングの機会を設けるよう心がけています。
お知らせ
昭和37年本邦で初の老年病学教室として当教室は誕生し、平成14年創立40周年を迎えました。冲中重雄先生(当時、第3内科教授との併任)によって開設され、昭和39年より吉川政己先生(故人)が初代専任教授、昭和54年-61年、原澤道美先生(故人)が2代目教授、昭和61年-平成7年、折茂肇先生が第3代教授として教室を指導しました。平成7年より大内尉義が第4代教授に就任し、平成25年より秋下雅弘先生が第5代教授に、令和6年7月より小川純人先生が第6代教授に就任し、現在に至っています。なお、医学部附属病院診療科再編成に伴い、当診療科の呼称を、平成10年4月、老人科より「老年病科」に改めました。
概要
診療体制
- 【外来】
当科では高齢者医療の専門家として全人的医療を行っております。<体の不調がどこからきているのかわからない><年のせい、といわれたけれど心配><症状はあるのだが、はっきりとした病名が分からない>、<少し物忘れが気になってきた>、<全体的に体を評価してもらいたい>など、臓器別の外来診療で解決が難しかった患者さんを中心に診療しています。より具体的な症状としては、物忘れ、食欲低下、意欲低下、歩行障害、息切れ、体重減少、不明熱などの高齢者に多い症候や原因不明の症候、ADLを大きく損ねるきっかけとなる症候に対して、幅広く対応しております。
特に、当科では、認知症の患者さんを多く診療しており、その分野の専門医がそろっています。また、骨粗鬆症を専門とする医師やCOPD、喘息、睡眠時無呼吸症候群などの呼吸器疾患を専門とする医師もおりますので、高齢者の幅広い症状に対応していきます。多くの疾患を合併し、たくさんの病院、診療所、診療科を受診している患者さんも多いと思いますが、本当は、ひとつの診療科で体全体をみながら診療してもらうほうがよい場合も多くあります。各々の病院、診療科から紹介いただければ、そのような患者さんを、一度全体的に評価して薬などの整理をするお手伝いもできると思います。 - 【専門外来】
当科では、以下のような専門外来を設けております。
物忘れ外来(認知症センター老年病科外来):平日午前
生活の様子の聞き取り、脳の画像検査、採血、場合によっては髄液検査(腰から針を刺して脳や脊髄を包む液体を調べる検査です)を行い、物忘れの原因を調べ、最適な治療、福祉サービスの導入を行います。認知症は、原因によっては、物忘れが治ることもありますので、原因を調べる検査は重要です。認知症は、物忘れ、見当識障害(時間や場所がわからなくなる)、失行(いままでできたことの手順がわからなくなる)といった症状が中心となりますが、それに伴い、機嫌が悪くなったり、家族にきつく当たったり、意欲が低下したり、といった精神的、心理的な症状が生じることもあります(周辺症状と呼びます)。周辺症状が、ご本人・家族の生活の質を下げる原因となっていることも多いです。物忘れ自体を直すことは困難なことが多いですが、周辺症状の治療を行うことにより、ご本人・ご家族が過ごしやすくなる場合があります。
フレイル・サルコペニア外来:平日午前
心身の機能低下がある状態で、運動や食事、社会活動への参加で回復する見込みのある段階を「フレイル」と呼びます。介護の必要のない健康寿命を延ばし、自立した人生を生きるためにフレイル対策は重要です。フレイルの原因として「サルコペニア」という状態があり、これは加齢に伴う筋肉量・筋力の減少を意味しています。当科の「フレイル・サルコペニア外来」では、フレイル・サルコペニアの評価、対策を行っています。新型コロナウイルス感染症の流行に伴う過度な自粛は、フレイルの促進につながります。感染対策とうまくバランスをとり、工夫した生活が求められます。
骨粗鬆症外来:平日午前
骨粗鬆症は骨の量や質が低下し、骨折しやすくなった状態です。骨粗鬆症は骨折するまで症状がなく、そのため気づかないことが多く、本来治療が必要な多くの患者さんが見逃されていると考えられています。また、一度骨折した方が、適切な骨折予防をされずに、二度目の骨折を起こしてしまう場合も多いです。当科では、適切な骨の評価(骨密度、採血)、治療を行います。また、たとえ骨が弱くなっても、転ばなければ骨折することはあまりありません。この意味で、転倒予防も重要な対策です。フレイル・サルコペニアに対する対策も同時に行われることが多いです。
高齢者息切れ外来:平日午前・金曜午後
喫煙が原因で肺が少しずつ壊れる「肺気腫」という病気があり、息切れが少しずつ進行します。肺気腫の患者さんはご高齢の方に多いです。しかし、肺気腫の患者さんのうち、大多数の方が診断されておらず、治療を受けられていないと考えられています。当科では、吸入治療や栄養療法など、肺の機能低下を防ぎ、生活機能を維持する工夫を行います。また、息切れは、肺や心臓、血液(赤血球の減少)などいろいろな原因で起こりますので、肺気腫以外の息切れの原因も同時に調べます。
高齢者お薬相談外来:月曜午前
高齢になると、複数の病気を持つことがあり、そのため薬の量が増える傾向にあります。さらに、肝臓や腎臓の機能が低下し、薬を分解し排泄する力が下がると、薬の成分が体に蓄積しやすくなり、副作用も起こりやすくなります。当科では、お薬手帳などを活用し、複数の医療機関から出されている薬の全体を把握し、生活機能に基づいた優先順位から、必要な薬、やめてもよい薬を判断します。高齢者にはあまり処方しないほうがよいとされる薬も存在し、そのような薬が処方されている場合は、別の薬に変更することもあります。介護が必要な患者さんに対しては、ご家族が管理しやすい服薬法の提案も行います。
睡眠時無呼吸外来:平日午前
当科では、若年者も含め、睡眠時無呼吸症候群の診療も行っております。睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が一定時間止まる病気で、日中の集中力の低下、夜間頻尿、逆流性食道炎などの原因となります。また心臓や血管に対するダメージも指摘されています。当科では、睡眠検査を行い、中等症から重症の患者さんに対して持続的陽圧呼吸による治療の導入を行います。睡眠検査は外来で行えますが、中等症の場合はさらに入院による詳しい睡眠検査が必要となります。
女性総合外来:金曜午後(平日午前の初診外来経由)
東大病院女性総合外来は、2003年7月に老年病科外来内に発足し、成人女性の心と身体の健康を守るために、全人的診療を行っています。高齢者では加齢の影響で、病気だけでなく精神面、社会的背景も含めた全人的医療が必要となります。そして、女性も女性ホルモンの動きに応じたライフサイクルのそれぞれの時期に、様々な心身の変化をきたすため総合的診療が求められます。また、当医局では、30年以上前から「女性ホルモンと加齢に伴う疾患」との関係を中心に、基礎・臨床両面から性差医学・性差医療に取り組んできました。このような背景から、「加齢と性差を専門とする医師の女性外来」として発足以来継続して診療を続けています。
女性外来を訪れる方の多くは更年期や更年期をきっかけに体調を崩された女性です。更年期障害は、女性ホルモンであるエストロゲンの急激な減少による症候群で閉経前後の約10年間におこるほてりや冷え、頭痛などの身体的症状、イライラ、鬱、不安などの精神的症状によって日常生活に支障を来したものです。これらの症状や期間は家族の理解など周囲のサポート体制、自身のこれまでの人生への思いなどにより大きく影響されます。また、更年期女性でなくともストレスや不規則な生活などによるホルモンの乱れなどにより更年期症状のような自律神経失調症状を含む様々な不調を来すことが少なくありません。
女性外来では、なるべく自らの言葉で症状や心理的・社会的背景を語って頂いています。血液検査、画像検査などにより、器質的疾患の鑑別を行った上でご希望を伺い、生活習慣の改善、漢方薬、西洋医学的な治療法から、その方の治療法を一緒に探していきます。 また、エストロゲンの減少は老化に伴う動脈硬化性疾患や骨粗鬆症、認知症といった介護が必要となる疾患の原因ともなります。更年期や、体調の乱れは自分の健康を考える最適の時期です。食習慣、運動習慣などの生活習慣を見直し、健診をうける習慣を持つことが重要です。自覚的な症状だけでなく、健診時の検査値の異常に関しても併せて診療させて頂き、検査値の改善、疾患、合併症の発症予防に結びつけることができます。一緒に考えていきましょう。当科女性医師が、できる限りのお手伝いをいたします。
- 【入院】
入院棟A13階北フロアを中心に、およそ10~15ベッドで入院診療を行っています。臓器にかかわらず、全人的に病気に取り組むことが当科の特徴です。特徴的な疾患としては、認知症に対する精査入院も受け入れています。高齢者の食欲低下精査入院も受け入れています。当科は65歳以上を主体として、入院治療を行っています。90歳代後半の方も珍しくありません。睡眠時無呼吸症候群の精査入院も行っており、このような疾患に関しては、若い方の入院も受け入れています。高齢者の心不全、肺炎、脳血管障害など救急外来から入院される比率が高いことも当科の特徴です。
治療方針
「病気をよくする」だけではなく、全人的に「病人をよくする」ことを目標としています。これは、疾病の治療はもとより、患者さんご本人が、ご本人らしく日々生活が営めるように体力の向上をめざし、自宅で生活するための社会資源の活用についても援助いたします。
対象疾患および得意分野
高齢者高血圧、高齢者高脂血症、生活習慣病予防、メタボリック症候群、高齢者糖尿病、甲状腺機能異常、骨粗鬆症、圧迫骨折、脊椎すべり症、認知症(物忘れ外来)、脳血管性認知症、アルツハイマー病、脳梗塞、パーキンソン病、女性ホルモン補充療法、更年期障害、漢方による治療、不整脈・心筋梗塞・狭心症・心不全・心臓弁膜症などの心疾患、起立性低血圧、閉塞性動脈硬化症、睡眠時無呼吸症候群、誤嚥性肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、急性・慢性呼吸不全、間質性肺炎、COPD呼吸リハビリテーション、禁煙指導、在宅酸素療法、脳梗塞後嚥下リハビリテーション、尿失禁なども含めた老年症候群など
主な検査と説明
外来
- 【PWV(Pulse Wave Velocity)脈派伝播速度検査】
動脈硬化、血管の硬さの指標となります。 - 【心臓超音波検査(心エコー)】
心臓のポンプ機能や弁の機能など、心臓における多くの情報を計測することができます。 - 【トレッドミル運動負荷試験(運動負荷心電図検査)】
心電計をつけてベルトの上を歩きます。労作性狭心症の診断を行います。 - 【ホルター心電図検査】
一日中心電計をつけて狭心症、不整脈の診断を行います。 - 【24時間監視型血圧測定】
携帯型の小さな血圧計により一日の血圧変動などを計測します。 - 【骨密度測定】
腰椎、股関節の骨の密度を測って骨粗鬆症を詳しく調べます。 - 【重心動揺検査】
体のバランスを測定して転倒のリスクを調べます。 - 【長谷川式簡易認知症スケール(HDS-R)検査】
認知症の程度を調べます。 - 【Mini-Mental State Examination(MMSE)検査】
認知症の程度を調べます。 - 【簡易嚥下誘発試験】
simple swallowing provocation test(Lancet 1999;353:1243)
我々が開発した方法で、誤嚥性肺炎のリスクを簡便に検出します。 - 【簡易酸素、呼吸モニターによる睡眠時無呼吸症候群のスクリーニング検査】
機械を自宅で装着し、その晩、自分で検査をして、翌日病院に器械を返却する。
入院
- 【認知症精査入院】
心理検査、高齢者総合的機能評価、頭部CT、頭部MRI、脳血流SPECT、髄液採取(Tap test) - 【高齢者総合的機能評価 (CGA)】
バーセルインデックス、HDS-R、Geriatric Depression Scale (GDS) などを用いてADL・知能スケールなど高齢者の日常生活に関わる機能を総合的に評価します。このCGA行うことで、その後のクリティカルパス、退院支援を有効にすすめ、入院期間の短縮につながります。 - 【24時間血圧測定】】
夜間の血圧異常(下がりすぎ、あがりすぎ)、早朝高血圧などを調べて、より効果的な血圧管理を行います。 - 【脈波伝播速度検査(PWV)】
動脈硬化(血管の若さ)の程度が定量的に把握できます。治療による効果の評価もできます。 - 【Polysomnography(ポリソムノグラフィー)】
睡眠ポリグラフともいいます。呼吸、脳波、心電図、いびき、などを夜間1晩検査します。睡眠時無呼吸症候群の診断に必須で、治療方針の決定に必要です。 - 【嚥下誘発試験(swallowing provocation test))および嚥下造影検査(videofluorography)】
嚥下障害を詳しく調べ、誤嚥性肺炎の予防のための指導を行います。 - 【サルコペニア・フレイル】
BIA法による筋量測定、歩行速度
科長