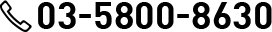カルシニューリン阻害薬(免疫抑制薬)が腎障害を引き起こす新たな原因を解明
2025年09月17日患者・一般
発表のポイント
- シクロスポリンAやタクロリムスといったカルシニューリン阻害薬(免疫抑制薬)の副作用に腎障害がありますが、発症するメカニズムは十分に解明されていませんでした。
- カルシニューリンを阻害すると、免疫反応が抑制されるだけではなく、腎臓の尿細管でのエネルギー産生が損なわれるため腎障害が起きることを明らかにしました。
- 本研究の成果は、カルシニューリン阻害薬による腎障害の予防や治療の方法を探索する礎となることが期待されます。
研究概要
シクロスポリンAやタクロリムスといったカルシニューリン阻害薬は、臓器移植や幹細胞移植の拒絶反応の予防、または自己免疫疾患(注1)の治療に多用される極めて重要な免疫抑制薬(注2)ですが、副作用として腎臓の機能が低下しやすいことが長年の課題です。
東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科の小田康弘研究員、西裕志准教授、南学正臣教授らの研究グループは、東京大学大学院医学系研究科 ライフサイエンス研究機器支援室の浜野文三江特任助教、北芳博准教授、ならびに米国国立衛生研究所の吉田輝彦客員研究員、Jeffrey B. Kopp主任研究員らの研究グループと共同で、シングル核RNAシーケンスや質量分析を用いて同薬が腎障害を引き起こす新しいメカニズムを解明しました。カルシニューリンを阻害すると、免疫反応が抑制されるだけでなく、多くのエネルギーを産生・消費する腎臓の近位尿細管でエネルギー産生が抑制されていました。この初期変化は長期的な腎臓の線維化(注3)や機能低下にも影響する可能性があり、本病態の予防や治療の方法を探索する礎となることが期待されます。
本研究成果は、2025年8月29日(米国時間)に米国科学誌「Journal of the American Society of Nephrology」にてオンラインで先行して発表されました。
研究内容
1.研究の背景
当院は歴史的に国内有数の臓器移植件数を誇っており、移植後も長期にわたり集学的な医療が行われています。カルシニューリン阻害薬は、臓器移植後や幹細胞移植後の拒絶反応(注4)の抑制や、自己免疫疾患の治療に多用される極めて重要な免疫抑制薬です。具体的には、世界保健機関の必須医薬品モデルリストにも挙げられているシクロスポリンAの他に、日本で開発されたタクロリムスがあります。治療目的の性質上、長期間にわたって内服する必要があることの多い薬剤ですが、副作用として腎臓の機能が低下することがあることが薬剤開発当初より課題となっています。特に、月単位や年単位で腎臓が線維化という構造変化を起こし腎臓の機能が低下する原因は、これまで明らかとなっていませんでした。
2.研究成果
近年、カルシニューリンという酵素は、細胞のエネルギー産生のために重要な役割を果たすピルビン酸脱水素酵素を活性化することが明らかとなりました。腎臓の構成細胞には、エネルギーを活発に産生・消費しながら尿生成プロセスの一翼を担う近位尿細管上皮細胞があることから、カルシニューリンの阻害により近位尿細管上皮細胞のエネルギー産生が阻害され、傷害を負った近位尿細管上皮細胞の影響で腎臓の線維化が引き起こされるのではないかという仮説を立て、研究をおこないました。
カルシニューリン阻害薬による腎障害を誘導したマウスの腎臓をシングル核RNAシーケンスで解析すると、傷害を負った近位尿細管上皮細胞の割合が増えていて、これらの細胞では細胞のエネルギー産生に関わる遺伝子の発現(注5)が低下し、線維化を促進する遺伝子や細胞老化に関わる遺伝子の発現が亢進していることが分かりました。細胞老化は、細胞のエネルギー代謝が障害されるなどの原因で引き起こされ、臓器の線維化を促進する要因となることが知られています。
近位尿細管上皮細胞で起きている現象を詳しく調べるため、ヒトの近位尿細管上皮細胞をカルシニューリン阻害薬添加培地で培養し、ガス・クロマトグラフィー質量分析などで解析したところ、近位尿細管上皮細胞のピルビン酸脱水素酵素の活性が低下し、細胞のエネルギー産生が低下し、細胞老化に特徴的な性質が現れ、線維化を促進する遺伝子の発現が亢進することが分かりました。そこで、ピルビン酸脱水素酵素を活性化する処置を行ったところ、細胞のエネルギー産生は改善し、細胞老化に特徴的な遺伝子の発現の変化は抑制されました。
ピルビン酸脱水素酵素を活性化することでカルシニューリン阻害薬による腎臓の線維化を抑制することができるかを調べるため、マウスに対してカルシニューリン阻害薬だけでなくピルビン酸脱水素酵素を活性化する化合物も併せて投与したところ、腎臓の線維化は抑制されました。また、カルシニューリン阻害薬の投与によって変化した、近位尿細管上皮細胞の傷害、細胞のエネルギー産生、細胞老化、線維化に関わる遺伝子の発現の変化は、この化合物を投与することで抑制されました。
これらのことから、カルシニューリンを阻害すると近位尿細管上皮細胞のエネルギー産生が阻害され、傷害を負った近位尿細管上皮細胞が線維化を促進するシグナルを出し、腎臓の線維化とこれによる腎臓の機能の低下が起こる一因となると考えられます。
3.今後の展望
カルシニューリン阻害薬が腎障害を引き起こすメカニズムが判明することで、本病態の予防や治療の方法を探索する道が開かれることが期待されます。例えば、特に腎臓の細胞でピルビン酸脱水素酵素を活性化する治療法が開発できれば、腎臓の細胞でのエネルギー産生障害が緩和され、カルシニューリン阻害薬による腎障害が軽減する可能性が考えられます。また、カルシニューリン阻害薬が免疫抑制薬として働くことと細胞のエネルギー産生を抑制してしまうことは異なるメカニズムによるものなので、エネルギー産生は抑制しないけれどもカルシニューリン阻害薬と同様のメカニズムで免疫反応を抑制する化合物を開発できれば、腎障害を引き起こさない新規の免疫抑制薬として役立つ可能性があります。

図:研究成果のまとめ
論文情報
雑誌名
Journal of the American Society of Nephrology
論文タイトル
Pyruvate dehydrogenase and cellular metabolism in calcineurin inhibitor—induced kidney fibrosis
著者
Yasuhiro Oda, Hiroshi Nishi*, Fumie Hamano, Teruhiko Yoshida, Yoshihiro Kita, Jeffrey B. Kopp, Masaomi Nangaku(*責任著者)
DOI
10.1681/ASN.0000000855
掲載日
2025年8月29日(オンライン)
研究者
小田 康弘(東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 届出研究員)
西 裕志(東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 准教授)
浜野 文三江(東京大学大学院医学系研究科 ライフサイエンス研究機器支援室 特任助教)
北 芳博(東京大学大学院医学系研究科 ライフサイエンス研究機器支援室 准教授)
南学 正臣(東京大学医学部附属病院 腎臓・内分泌内科 教授)
共同研究機関
米国国立衛生研究所
研究助成
本研究は、JSPS科研費 JP23KJ0437, JP25K19483, JP24K11425, JP23H02924の助成、JST次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2108、AMEDの課題番号JP22zf0127006、ならびにNIDDK Intramural Research Programの支援を受けて実施しました。
小田康弘は、本研究期間中に日本学術振興会特別研究員DCとして支援を受けました。
用語解説
(注1)自己免疫疾患:
免疫反応は、通常は細菌などの異物を排除するために起こり体を守る役割を果たしますが、時に自身の正常な組織(臓器など)を標的としてしまい、自身の組織を傷つけてしまうことがあります。このようなメカニズムで発症する病気を総称して自己免疫疾患といいます。一例として、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、腎炎の一部、ネフローゼ症候群の一部などが挙げられます。
(注2)免疫抑制薬:
好ましくない免疫反応を抑えることを目的とする薬剤の総称です。
(注3)線維化:
組織(臓器など)に線維性の成分が多く含まれるようになることです。線維性の成分が増えることで、組織の正常な構造が邪魔をされ、その組織の本来の機能が阻害されてしまうことが多くみられます。
(注4)拒絶反応:
他の人から自身に移植された臓器や造血幹細胞が、自身の免疫系によって自己の組織(臓器や細胞など)ではない異物だと認識され排除されようとする反応のことです。移植された臓器などが傷つき機能を失ってしまう原因になります。
(注5)遺伝子の発現:
タンパク質は体の中で様々な機能を持ち、膨大な数の種類が存在します。タンパク質が合成されるプロセスは、一つ一つの細胞の中で、タンパク質の設計図である遺伝子を読み取りDNAの配列をRNAとして写し取ることから始まります。この過程のことを「遺伝子の発現」と呼びます。