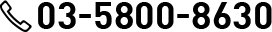“特定の脳血流パターン”がADHD治療薬の効果を予測する手がかりに
2025年07月30日患者・一般
―痛みとの意外な関係―
発表のポイント
- ADHDを併存する慢性疼痛患者さんでは、脳の楔前部(けつぜんぶ)に高い血流がみられ、治療薬によってその血流が低下し、痛みや症状の改善と関連していることを明らかにしました。
- 慢性疼痛とADHDの両方に関わる脳領域の血流パターンを、SPECT画像を用いて大規模に解析した初めての研究です。特に、楔前部の血流が治療前の重症度や治療後の改善例に関連していたことは、新たな知見として注目されます。
- 脳画像を用いて、ADHD治療薬が有効な慢性疼痛患者を識別できる可能性があり、今後の診断や個別化治療に役立つことが期待されます。特に、楔前部の血流パターンが治療効果を予測するためのバイオマーカーとなれば、より効果的な治療選択につながる可能性があります。
研究概要
長く続く痛みに悩まされながらも検査では異常が見つからない、そのような慢性疼痛に苦しむ方は少なくありません。神経や脳の働きの乱れが関わっていると考えられていますが、治療が難しく、患者さんの生活に大きな影響を与えています。最近では、こうした痛みを持つ患者さんに、注意欠如・多動症(ADHD)を併せ持つケースが多いことが分かってきました。
本研究では、ADHDを併存する慢性疼痛患者65名を対象に、脳の血流を可視化するSPECT検査(注1)を行い、治療薬との関係を調べました。その結果、「楔前部(けつぜんぶ)」という脳の領域で血流が高く、ADHD治療薬の服用により血流が下がり、痛みや不安、集中力の改善と関連していることが明らかになりました。このような脳の血流パターンは、薬が効く可能性のある患者さんを見分ける新たな手がかり(バイオマーカー、注2)になると期待されます。
研究内容
1.研究の背景
痛みが長期間続くにもかかわらず、画像検査や血液検査などの診断では異常が見つからないといった「原因のはっきりしない痛み」に悩む患者さんが数多く存在します。このような慢性の痛みは、従来の治療が効きにくく、日常生活や仕事に支障をきたすことも少なくありません。最近では、このような痛みには神経や脳の働きの乱れが関係している可能性が注目されており、特に「注意欠如・多動症(ADHD)」との関連が指摘されています。ADHDは集中力が続かない、気が散りやすい、落ち着きがないなどの症状を特徴とし、子どもだけでなく大人にも見られる発達特性(注3)です。近年の研究では、慢性の痛みを訴える人の中には、ADHDを併せ持つ人が多いことが報告されており、その背景にある脳のメカニズムを解明することが求められています。
2.研究成果
本研究では、ADHDを併存する慢性疼痛患者65名を対象に、脳の血流を調べるSPECT(単一光子放出コンピュータ断層撮影)という画像検査を用いて、段階的な薬剤選択と調整を行う治療アルゴリズムに基づくADHD治療(図1)と、その後の脳の変化や症状の改善との関係を検討しました。
解析の結果、「楔前部(けつぜんぶ)」と呼ばれる脳の一部で、治療前に血流が高まっていることが明らかになりました(図2)。この部位は、自分自身の意識や注意、感情の調整に関わる領域として知られています。治療薬(主にメチルフェニデートやアトモキセチン)の服用により、この領域の血流が低下する傾向がみられました。さらに、この治療アルゴリズムによって、痛みの強さ、不安、うつ、痛みに対する破局的な思考(痛みをより大きく捉えてしまう傾向)、ADHDの指標、そして総合的な全般的重症度スコアにおいても改善が確認されました(図3)。
これらの結果は、脳の血流パターンが、治療効果を見極める新たな手がかり(バイオマーカー)になる可能性を示唆しています。

図1:ADHD治療アルゴリズム
本研究では、ADHDを併存する慢性疼痛患者に対して、症状や副作用に応じて段階的に薬剤を調整する治療アルゴリズムを採用しました。初期治療には、ADHDの注意力や衝動性の改善効果が期待されるメチルフェニデート徐放錠を用い、効果が不十分または副作用がある場合には、同様にADHDの症状に対して有効性が認められているアトモキセチンへ切り替えます。さらに、必要に応じて、ADHDに伴う情緒や行動面の症状の調整を目的として、アリピプラゾール(抗精神病薬)やクロニジン(自律神経調整薬)を追加する選択肢も設けられています。

図2:ADHD治療による脳血流の変化
ADHDを併存する慢性疼痛患者における脳の働きを調べるため、SPECTという画像検査を用いて治療前後の血流の変化を可視化しました。左側の縦に並べた2つの図は、段階的な治療アルゴリズム全体を通じた脳血流の変化を示しています。治療後には、脳の「楔前部(けつぜんぶ)」と「島皮質(とうひしつ)」という領域で血流が有意に低下していました。楔前部は注意や意識、身体感覚の制御に関わり、島皮質は痛みや情動、自律神経の調整に深く関係しています。これらの領域の過活動が治療により抑えられることで、痛みや精神症状の改善につながっていると考えられます。中央の図は、治療薬のうちメチルフェニデートを使用した患者に限定した前後比較を示しており、治療後には楔前部で同様の血流低下が見られました。さらに右側の図では、治療前の脳血流と、医師による全般的な重症度(CGI-S)の評価との関係を解析しました。その結果、重症度が高いほど楔前部の血流が高まっていることがわかり、これらの脳領域の血流が症状の重さと関係している可能性が示されました。つまり、ADHD治療薬によって血流が改善する部位である楔前部は、慢性疼痛の重症度ともぴったり一致するため、ADHD治療薬による改善を予測するバイオマーカーになる可能性があります。

図3:ADHD治療前後での評価項目の変化
ADHDを併存する慢性疼痛患者に対して、症状や副作用に応じて治療薬を段階的に調整する方法で治療を行い、その前後で複数の臨床指標を用いて評価しました。その結果、痛みの強さが有意に軽減したほか、不安やうつの程度、痛みに対する破局的思考(「痛みが今後も悪化する」「痛みに耐えられない」といった極端な捉え方)も改善が見られました。また、注意力の散漫さや多動・衝動性といったADHDの症状についても改善が認められました。さらに、医師による全般的な重症度の評価においても、治療後には症状の軽減が確認されました。これらの結果から、ADHDの治療薬が疼痛や精神症状を含めた多面的な改善に寄与する可能性が示唆されました。

図4:ADHD治療薬の効果を予測(典型症例)
ADHD治療薬アトモキセチンを1日25 mgで服用し、痛み(慢性腰痛)や注意力の問題などが大きく改善した患者さんの脳画像です。治療前は、「楔前部(図内の矢印部分)」で血流が高く、前頭葉(図内の点線部分)では血流が低下していました。治療後には楔前部の血流が低下し、逆に前頭葉の血流が増加していました。これらの変化は、症状の改善と一致しており、脳の活動バランスが整ったことを示している可能性があります。このような血流のパターンは、薬の効きやすさを予測する手がかりとなるかもしれません。
3.社会的意義や今後の展望
慢性的な痛みに苦しむ方の中には、ADHDの診断を受けていないまま現在に至り、従来の痛み止めや心理的アプローチでも十分な効果が得られないケースがあります。本研究の結果は、ADHDという発達特性と慢性疼痛の関係を「脳画像」という客観的なデータで示した点で大きな意義があります。さらに、楔前部の血流パターンを見ることで、ADHD治療薬が効果を発揮する可能性が高い患者さんを事前に見極められる可能性があり(図4:改善した患者さんの典型的な血流パターンの変化)、診断や治療方針の個別化につながることが見出されました。
今後は、ADHDを持たない患者さんとの比較や、他の痛みのタイプに対する脳活動の違いを検討することで、より広い視点から治療戦略の構築を目指します。将来的には、画像診断を活用した「脳に基づく痛みの診断・治療」の実現に貢献することが期待されています。
4.授賞
本研究成果は、第121回 日本精神神経学会学術総会(2025年)で発表され、「優秀発表賞」と「精神神経学雑誌投稿奨励賞」を授賞しました。
学会発表
学会名
第121回 日本精神神経学会学術総会
発表タイトル
慢性疼痛患者の楔前部高血流は、ADHD治療薬による痛みと認知機能の改善を予測するバイオマーカーとなり得る
発表者
笠原 諭、高橋 美和子、相馬 努、森田 泰斗、佐藤 直子、松平 浩、百瀬 敏光、丹羽 真一
発表日
2025年6月19日
関連論文
雑誌名
Frontiers in Pharmacology
論文タイトル
Precuneal hyperperfusion in patients with attention-deficit/hyperactivity disorder-comorbid nociplastic pain.
著者
Miwako Takahashi*, Satoshi Kasahara*, Tsutomu Soma, Taito Morita, Naoko Sato, Ko Matsudaira, Shin-Ichi Niwa, Toshimitsu Momose(*責任著者)
DOI
10.3389/fphar.2024.1480546
掲載日
2024年10月17日(オンライン)
研究者
笠原 諭(東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター 特任臨床医)
森田 泰斗(東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター 病院診療医)
佐藤 直子(東京大学医学部附属病院 看護部 看護師)
百瀬 利光(東京大学大学院 工学系研究科(工学部) 客員研究員)
共同研究機関
量子科学技術研究開発機構 量子医科学研究所
PDRファーマ株式会社
福島県立医科大学 会津医療センター
研究助成
本研究は、文部科学省科学研究費助成事業(科研費:JP24K13083、JP20K07755)の支援を受けて実施しました。
用語解説
(注1)SPECT(単一光子放出コンピュータ断層撮影):
SPECT(スペクト)とは、脳などの臓器の血流や代謝の状態を調べるための画像検査です。放射性の薬剤を注射し、その分布を特殊なカメラでとらえることで、脳のどの部分がどれくらい活動しているかを可視化できます。CTやMRIでは見えにくい「機能の変化」をとらえるのに適しており、脳の働きの特徴や異常を調べるのに役立ちます。
(注2)バイオマーカー:
バイオマーカーとは、病気の診断や重症度の判定、治療の効果を予測するための「生体の目印」です。血液検査や画像検査などで得られる情報が使われます。今回の研究では、脳の血流の特徴がバイオマーカーになる可能性が示されました。
(注3)発達特性:
発達特性とは、生まれつきの脳の働き方や感じ方の違いによって、行動や考え方に独自の特徴が見られることを指します。たとえば、集中しにくい、人づきあいが苦手、こだわりが強いなどの傾向があります。困りごとが少ない場合は「障害」ではなく「特性」として捉えられ、周囲の理解や支援があれば、その人らしく生活することができます。