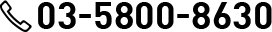東大病院の目指す方向
「東大病院の目指す方向2011~2012年度版」について
東大病院は、“臨床医学の発展と医療人の育成に努め、個々の患者に最適な医療を提供する”という理念の達成をめざし、日本の医学・医療の拠点として社会のニーズに応えてきた。法人化後、運営費交付金や定員の削減の中でも、自助努力により診療機能を高め、稼働額年372億円前後、稼働率90%前後、平均在院日数13日前後という診療実績をあげ、高い評価を得ている。今後、診療面では、入院棟Ⅱ期(新病棟)の早期実現を目指し、統合的な診療機能を飛躍的に高めたインテグラルホスピタルとして当院の診療理念の実現を図っていきたい。
一方、経営において膨大な自助努力が求められた結果、東大病院においても、診療に割く時間やエフォートが大きく増加し、研究は時間やエフォートの上で圧縮されている。臨床医学研究と先端医療開発は、当院が社会から期待されている重要なミッションであり、一層強力に進める必要がある。今後、研究・開発面では、クリニカルリサーチセンター(臨床研究棟)の早期実現を目指し、統合的な研究・開発機能を飛躍的に高めた臨床医学研究の国際的拠点として当院の臨床研究と開発の理念の実現を図っていきたい。
武谷前病院長と前執行部は法人化の2期目を迎えるにあたり、東大病院がその理念に沿ったさらなる社会貢献を通じて国民の負託に応えるために、東大病院の目指す方向2009-2010年版を策定した。この目指す方向2009-2010年版に示された行動目標の相当部分は、教職員の努力により達成途上にある。一方で、残された課題も少なくない。この間、東大病院を取り巻く社会の状況も大きく変化し、世界に例をみないスピードで進行する少子高齢化社会の中で、医療提供体制が悪化し、最後の砦としての大学病院に対する社会の期待は確実に大きくなっている。この期待を受け、東大病院は、(1)高度な診療の実践、(2)国際的に評価される医学研究、(3)全人的医療人の養成、という三位一体の高いミッションの達成に向けて大きく飛躍すべき段階にある。そのために、引き続く改革の推進や経営基盤のさらなる安定化は必須である。同時に、これらは、あくまでも手段であって、目的ではない。東大病院への期待や評価の尺度は、あくまでも上記の三つのミッション、とりわけ明日の医療・医学を切り拓く国際的に評価される臨床医学の研究・開発と実践であると考える。
一方、このようなミッション達成の外的条件である大学病院の診療・研究・教育に対する人的・財政的支援は未だ極めて不十分である。加えて、本年3月11日の東日本大震災により国全体が受けた人的・経済的損失の痛みを分かち合い、復興に向けての支援を率先して推進することが求められている。このような状況に際して、東大病院は、自ら切り開いてきた当院の発展段階と新たな社会情勢をふまえた、新しい課題の設定とその実現に向けた行動目標を策定し、この難局を克服していかねばならない。今、特に求められているのは、法人化に対応した当院の運営や経営における改革の高みに立ち、法人化で得られた自由度を最大限生かした、当院のミッションの全面的達成に向けた積極的かつ迅速な改革の努力である。このような基本構想のもとで、現執行部で、検討を重ねて策定したものがこの目指す方向2011-2012年度版である。2009-2010年版との継続性は十分に考慮しつつ、その単なる延長線上のものではなく、当院の新しい発展段階にふさわしい新たな課題の達成を見据えた、重点的な行動目標を、簡潔にまとめた。章立てとして、1. 診療機能のさらなる向上と入院棟Ⅱ期構想の実現、2. 臨床研究と先端医療開発のさらなる活性化とクリ二カルリサーチセンター構想の実現、3. 診療・研究・教育のバランスのとれたミッション達成に向けた教職員の増員と戦略的配置、4. 東大病院の将来を支える人材養成、5. 機動性の高い組織運営体制のさらなる確立、とした。本指針により、東大病院が現在どのような状況にあり、いかなる方向に進むべきかを全職員が良く理解し、当院の機能や活動が向上することを願っている。私は、東大病院のミッションに立ち返り、当院の理念を堅持し、目指す方向2011-2012年度版の達成に向け、誠心誠意努力を行いたい。現執行部の任期である2011-2012年度版の二年間、東大病院が一段と飛躍する時期となることを切望してやまない。
平成23年11月21日
東京大学医学部附属病院
病院長 門脇 孝
1. 診療機能のさらなる向上と入院棟Ⅱ期構想の実現
- 急性期医療・先進医療を中心に診療機能の向上を図るとともに、「国際診療部」の設置を進める
成人や周産期、新生児・小児に対する高度急性期医療を行う体制のさらなる充実を図ると共に、先進医療・高度医療の実践を進める体制を整備し、急性期医療、先進医療・高度医療のバランスが取れた診療体制を構築していく。また、国際的な拠点病院となることを目指し、海外からの患者受け入れ、医師の招聘、研修生の受け入れなどに関する課題を検討し、「国際診療部(仮称)」の設置を進める。 - 医療の質の評価を行い、質の向上につなげる
新たな臨床指標の策定や通年型の患者アンケートの実施などにより、医療の質の評価を行って、医療の質のさらなる向上を図り、病院の国際化も視野に据えたJCI(Joint Commission International) 認定の取得に向けた議論を開始する。 - 医療安全、院内感染の防止策の更なる強化と評価体制の構築を図る
院内感染対策を一段と強化し、手洗い実施率の大幅な向上や抗菌薬の適正使用をモニタリングするシステムを構築すると共に、医療安全対策情報の周知徹底や伝達の体制の強化をさらに進める。 - 診療科間・職種間の連携を強化するとともに、地域における医療連携を推進する
専門分化された内科系や外科系は、連携をより強化して全体でまとまって統合的に診療や教育を行う体制を構築すると共に、院内横断的な専門チームの拡充、ケースワーカーやコーディネーターなどの増員、地域における医療連携のさらなる推進を図る。 - 入院棟Ⅱ期の実現に合わせた診療機能の強化・再編を行う
入院棟Ⅱ期と他の診療棟との連携、機能分担の再編、予防医学的観点からの検診部の充実などを図り、全体として診療の連携がより強化された体制の構築を目指す。
2. 臨床研究と先端医療開発のさらなる活性化とクリニカルリサーチセンター構想の実現
- 疾患研究、橋渡し研究、臨床研究を有機的に連携するための体制を整備する
疾患研究、橋渡し研究(TR)、臨床研究を有機的に連携させ、サイクル型で推進する体制の構築を目指す。このため、TRセンターの常設化に向けた体制整備を行い、22世紀医療センター、最先端臨床研究センター、ティッシュエンジニアリング部、医工連携部、および臨床研究支援センターの連携体制を構築する。 - 早期・探索的臨床試験拠点整備事業を推進する
早期・探索的臨床試験拠点整備事業を推進するため、早期・探索開発推進室やPhase Iユニット、認知症ボードなどを新設し、また臨床研究支援センターをさらに拡充する。Phase Iユニットは当面の対応と、入院棟Ⅱ期建設後の中・長期的な対応に分けて検討を行う。 - 臨床研究支援センターを中心とした研究支援体制の一層の充実を図る
質の高いアカデミア主導の臨床研究プロジェクトを推進するために、臨床研究支援センターの運営体制の強化とともに、ゲノム医学センターやCPC(Cell Processing Center)の運用体制の強化を行う。このため人事・財務など体制整備や支援を行い、研究支援体制の充実を図る。 - 研究倫理の確立にむけた取組みを徹底する
科学性・倫理性・透明性の高い臨床研究を推進するために、研究における高い倫理意識を一層徹底し、研究費の適正経理のための教育を行い、機関経理のさらなる充実、利益相反への適切な対応を行う。 - クリニカルリサーチセンター構想の具体化に向けたハード・ソフト両面の準備を進める
クリニカルリサーチセンター構想に基づき、大学本部と連携しながら、要求水準書、フロアプランの具体化など、着工に必要な全ての準備を整える。研究スペースやリソース・機能の充実と集約化を実現し、ハード・ソフト両面のバランスを取りながら、病院全体の研究環境の向上につながる計画を策定する。
3. 診療・研究・教育のバランスのとれたミッション達成に向けた教職員の増員と戦略的配置
- 病院教授などの称号付与制度を創設する
多様な人材の登用と人事の活性化を図る目的で、教職員への称号(教授、准教授、講師)付与制度などの創設に向け、対象者、条件などを検討する。なお、当面は准教授を対象とした病院教授の称号付与制度を創設する。当院の教職員以外に対する称号付与制度としての臨床教員(教授、准教授、講師)制度については検討を継続する。 - 戦略的に人員を配置し、教職員の活性化を図るための新たな教職員配置のあり方の検討を行う
これまで行われてきた流動化とは異なる仕組みを教員の再配分法として導入できるかについて検討するとともに、中央施設部門の教職員配置のあり方について、業務内容や労務環境の状況に応じた柔軟な方法の導入を検討する。 - 麻酔科や外科系医師の確保や支援を図るとともに、現場要望の吸収システムを検討する
麻酔科や外科系医師のキャリア構築やライフワークバランスの向上を支援する体制を整備するとともに、外科系診療をさらに発展させるための人員の増強を行う。各種要望を病院執行部に提案しやすいシステムの設置を検討する。 - 男女共同参画、家族介護を行う教職員のための支援制度を拡充する
病院診療医制度の拡大を図ることにより、家族の介護を行う医師や妊娠中の女性医師の継続的な臨床活動の機会を確保する。病児・病後児保育の検討など、院内保育園の一層の充実を図り、教職員が働きやすい職場環境の整備を行うことで、男女共同参画をさらに推進する。 - 教職員が本来業務に専念できるようなクラークなどの配置を検討する
教職員が本来業務に専念し積極的に役割拡大ができるように、学術活動の支援もできるクラークなどの増員を検討する。また診療機能向上・患者サービス向上、教職員の負担軽減を目的に、積極的に増員を検討する。
4. 東大病院の将来を支える人材養成
- 総合研修センターの機能をさらに強化する
総合研修センターが、研修医教育のみならず、病院の教職員全体の教育や研修に中心的な役割を果たすような体制の強化を進め、e-ラーニングの質の向上や研修医に関する包括的な情報の発信なども行っていく。 - 学生実習および教職員の研修プログラムを改善する
学部学生については、臨床参加型の実習をさらに充実させる。研修プログラムについては、研修医の評価や要望を継続的に調査してプログラムの改善を図る体制を整備する。また看護師に対してはキャリアラダー制度をさらに充実させ、それ以外の教職員についても研修体制の強化を図る。 - 教職員のキャリア構築支援を行う体制を強化する
さまざまな分野において、高い専門性をもつ教職員となるための教育や、そのキャリアパスを支援する体制を強化する事により、教職員のモチベーションを高め、専門的な能力の向上を図る。 - 研究部門を支える人材を養成する
研修医や若手医師が最先端の研究に触れる機会を設ける為に、臨床研究者育成プログラムへの参加を促すとともに、各種研究セミナーを開催し、研修医と研究者の交流を図る。指導医クラスの医師が研究に十分な時間がさけるよう、支援体制を構築する。 - 高度医療クラークの養成プログラム確立に向けた取り組みを推進する
高度医療クラーク養成を行うプログラムを策定し、現場での教育を行って専門的な能力を養成し、医師などの負担軽減や医療の質向上を図る。
5. 機動性の高い組織運営体制のさらなる確立
- 経営資源を最大限に活用した病院運営・経営を実践する
人件費枠の管理、要員管理、病院運営上必要な人事給与制度改正の権限について東大病院が機動的に対応できるよう、その仕組み作りについて大学本部と検討する。 - 国の制度改革を見据えつつ、自律的で強固な財務基盤を確立する
医療制度、交付金制度などの制度改革を見据え、当院の果たすべき使命を社会に訴える。効率的な資産管理システムの確立、医療、医薬品・機器の標準化、後発品の適正使用などを通じ自律的で強固な財務基盤の確立をめざす。 - 組織のスリム化、意思決定・実行の迅速化に向けた取り組みを強化するとともにチーム医療・職種間コミュニケーションの推進を図るための体制を構築する
中央施設部門、委員会の整理統合による組織のスリム化を通じ、意思決定と実行の迅速化を図る。院内横断的な専門チームの一層の充実を図ると共に、院内のさまざまな意見を汲み上げる体制を整備する。診療・医事情報の連携、国立病院管理会計システム(HOMAS)の改良、活用を通じ根拠に基づく病院運営・経営をめざす。 - 災害医療マネジメント部新設をはじめとした危機管理体制の確立に向けた体制整備を行う
災害医療学の確立と、大規模災害医療活動マネジメント人材育成を目的とした災害医療マネジメント部設置に向け具体的な役割を検討する。自然災害にとどまらず防犯体制、パンデミック対策など危機管理体制を再検討する。 - 広報機能を発展させ、社会への情報発信を推進する
プレスリリース、広報誌、ホームページなどを通じ、診療・教育・研究など、当院のさまざまな活動について情報発信を継続して行う。さらに、当院の特徴的な活動についてより一層社会の理解を得られるよう、メディアとの懇談会を定期的に開催することを引き続き行うとともに、市民公開講座などの開催を推進する。