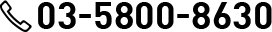東大病院の目指す方向
「東大病院の目指す方向2025~2026年度版」の作成にあたって
東大病院は「臨床医学の発展と医療人の育成に努め、個々の患者に最適な医療を提供する」ことを理念とし、その実現のために「患者の意思を尊重する医療の実践」、「安全な医療の提供」、「先端的医療の開発」、「優れた医療人の育成」を目標としてまいりました。近年、社会からの要請に応え、より質の高い医療を提供し続けるために、「働きやすい職場環境の実現」を新たな目標に加え、職員一人ひとりがその能力を最大限に発揮できる組織づくりを推進してまいります。この理念と目標を達成し、東大病院が社会から求められている日本の医学・医療の拠点としての機能を果たすために、2年毎に「東大病院の目指す方向」と題するアクションプランを立ててきました。この計画は必ず実行する行動計画として、中間評価、最終評価という PDCA サイクルを回して自己点検を行っているものです。
新しい行動計画は、1. 診療、2. 研究、3. 教育・研修、4. 人事・労務、5. 運営の5つの分野について、担当副院長を中心にプランを作成し、さらに執行部でも議論を重ね、「東大病院の目指す方向 2025~2026年度版」として策定致しました。いずれも今後東大病院が大学病院としてのミッションを果たし、さらなる発展を目指すために重要な内容となっていますので、皆様には是非ご一読いただければと思います。
特に今回の計画では、組織全体の風通しを向上させ、職員が互いを尊重し、協力し合える働きやすい職場環境づくりを重視しています。診療面では、多職種連携を強化し、高度急性期医療機関として地域医療に貢献するとともに、大学病院として高度・先進医療を積極的に推進します。具体的には、移植医療やゲノム医療といった最先端医療のニーズに応え、集中治療室などの高機能病床の効率的な運用体制を確立します。研究面においては、臨床研究中核病院、がんゲノム医療中核拠点病院や橋渡し研究拠点にふさわしい臨床研究を推進し、医療イノベーションの創出を実現します。教育面においては、将来の東大病院を支える高度な医療人材を育成すべく、多彩な教育プログラムによる支援体制を確立し、個々の能力と意欲を発揮できる教育・研修環境の整備を行い、人材育成を強化します。運営面では、病院重要業績指標(KPI)の設定とその達成に向けた取組やコスト削減を中心とする経営改善を推進するとともに、社会情勢に合わせた最適な病床運営を目指します。また、働き方改革を推進するため、業務の適切な分担と共同体制の構築を進めるとともに、ICTの活用による労務環境の改善にも積極的に取り組みます。
これらの目標達成には、職員一人ひとりの協力が不可欠です。当院は、すべての職員が能力を最大限に発揮できる職場環境を実現し、職員一丸となって東大病院のさらなる発展に貢献してまいります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。
2025年6月吉日
東京大学医学部附属病院
病院長 田中 栄
東大病院の目指す方向2025~2026年度版
1.診療
高度医療と先端的医療を担う当院の使命を全うするため、組織体制及び業務内容を見直し、病院機能の充実を図り、安全で安心な医療を提供するとともに、医療の質向上と効率的な運用を実現する。高度急性期機能を有する病床を効果的に活用するとともに、安定した病床稼働を目指す。更に、多職種が専門性を生かして貢献し、相互に信頼し連携して患者に最適な医療の提供を目指すとともに、地域医療機関との連携及び医療の国際化を推進する。
- 当院に求められる高度かつ先端的な医療の機能を充実させ、効率的に提供すると同時に、高難度手術の増加に対応できるよう手術部の運用 などの体制を整備する。
- 患者の意思を尊重し、多職種が相互に信頼し連携して、安全・安心で良質な医療の提供に取り組む。
- 高度急性期医療の提供にあたり集中治療室(ICU)など高機能病床を効果的に活用できる運用体制を確立するとともに救急医療体制のさらなる充実を図る。
- 患者の状況に応じて適切な医療の提供ができるよう、適正で効率的な病床運営を推進する。
- 地域医療機関との役割分担の明確化や協力体制を強化し更なる地域医療連携を進めるとともに、需要が高まる医療の国際化の推進を図る。
2.研究
医療イノベーションと、最適な医療が選択できる科学的根拠を形成する臨床研究を推進する。また、研究DXを通じて、他学部等との連携による革新的最先端異分野融合研究プロジェクト、トランスレーショナルリサーチ、AI等の先端科学技術を取り入れた研究の促進を図る。
- 臨床研究中核病院として、医療法上の特定臨床研究(臨床研究法の規定に基づいて実施する臨床研究、医師主導治験、企業治験)等のより一層の活性化を図る。
- 基礎医学系教室、他学部、他機関および民間企業との産学官連携を通じて、革新的最先端異分野融合研究プロジェクトの創出、トランスレーショナルリサーチの推進を図る。
- 研究DX(デジタルトランスフォーメーション)を促進して、医療ビッグデータ活用基盤を構築する等し、生成型AI等の先端科学技術を取り入れた研究の推進を図る。
- 研究活動の基礎となる研究者の安全と健康を守るため、化学物質および実験機器類の適正管理を徹底するとともに、研究室における安全管理体制の強化と教職員の安全意識の向上を図る。
3.教育・研修
多職種連携やタスクシフト・シェアの推進及び人材の定着に向け、各職種の専門性の向上、教育機能・環境を整備し、人材育成を強化する。
- 患者にとって安全性の高い医療を実現するため、教職員は診療現場や職場におけるチームワークを強化し、さらにタスクシフト・タスクシェアを踏まえた多職種連携の教育・研修を実施する。
- 診療参加型臨床実習の推進及び研修医教育の充実と研修環境の整備を進めるとともに、専門医制度への対応を強化し、社会のニーズに応える優れた医師の育成を推進する。
- Faculty Development/Staff Developmentプログラムを通じた教職員の指導力の向上により、高度な医療人材の育成を目指す。
- 教職員一人ひとりの能力と意欲がより発揮される教育・研修の推進とそのための環境整備を着実に進める。
- 医療経営、医療データの分野で未来を切り拓く高度人材の育成に向けた教育・研修を推進する。
4.人事・労務
働き方改革を推進し、時間外・休日労働の縮減に取り組むとともに、教職員の健康管理や業務効率化等のため勤怠管理システムの機能拡充を行う。また、両立支援を推進する等、働きやすい職場環境を整備する。
- 時間外労働の短縮に向けた取組みを進めるとともに、長時間労働者に対する健康管理や業務効率化等のため勤怠管理システムの機能拡充を行う。
- タスクシフト・タスクシェアを更に推進し、医療従事者の勤務環境の改善を図るとともに、安定的な業務遂行が可能となるよう制度の検討を行う。
- 診療体制の維持や教職員のニーズを踏まえた両立支援体制の整備を行う等、就労環境の向上に取組む
5.運営
全ての教職員が協働し、個々の患者に最適な医療を継続的に提供するとともに、働きやすい職場環境の構築を推進する。また、病院の経営基盤の安定化を図るため、病床稼働率の向上やコスト削減をより一層推進するとともに、社会情勢や医療ニーズに応じた適正な受入れ体制や病床数を検討する。更に、中長期的な病院再開発計画の見直しや医療DXを加速させ、持続可能な医療提供体制の構築を目指しながら、接遇の強化や患者療養環境の更なる充実に取り組む。
- 個々の患者に最適な医療を継続的に提供するため、全ての教職員が協働し働きやすい職場環境の構築を推進する。
- 病院重要業績指標(KPI)の達成に向けた取り組みを強化するとともに、病床稼働率の向上とコスト削減を軸に経営改善を推進する。更に、社会情勢に応じた最適な病床運営の在り方を検討する。
- 中長期の再開発整備計画と将来構想の企画・立案を進めるとともに、短期的には患者や教職員のニーズに応じたインフラ整備を推進する。
- 法令遵守及び各種制度の改正に適切に対応するとともに、院内のセキュリティ対策を見直し、更に院内外に向けた広報活動の強化と改善を図る。
- 安全性・利便性・快適性に配慮した医療サービスの提供体制を実現するため、医療DXの活用や接遇教育等を推進し快適な患者療養環境を構築する。