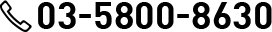てんかんセンター
近年、てんかんを取り巻く環境は大きく変化しています。てんかん診療に対する社会的ニーズの高まりを背景に、新しい治療薬の登場や各種診断法の精度向上、外科治療法の進歩などが相まって、てんかん診療は新たな時代に突入しています。このような変化に対応し、最善のてんかん診療を行うためには、診療部門や職種、さらには施設を超えた緊密な連携が必要となります。そのような院内外の連携を促進することを目的として東京大学医学部附属病院てんかんセンターが開設されました。
お知らせ
- てんかんセンターでは、第1~第4月曜日の午後、関連診療科の担当医師が週替りで初診外来を担当します。外来予約センターで予約をお取りください。初診時には現在おかかりの施設の紹介状を持参してください。
- 紹介状の宛先診療科や医師が決まっていない場合には、「てんかんセンター」宛で結構です。ご紹介の内容に応じて、適切な診療科の医師が対応いたします。
概要
診療体制
てんかんセンター初診外来を窓口として、てんかん診療に関わるすべての診療科・部門の医師、看護師、臨床検査技師、臨床心理士、作業療法士、ソーシャルワーカー、薬剤師が連携して、院内横断的チーム医療を実施します。必要に応じて近隣の医療機関とも協力して診療を継続します。
| 検査部担当医 | 代田悠一郎(センター長) |
| 小児科担当医 | 内野 俊平、寺嶋 宙 |
| 精神神経科担当医 | 水谷 真志 |
| 脳神経外科担当医 | 嶋田 勢二郎、永田 圭亮、藤谷 茂太 |
| 脳神経内科担当医 | 濱田 雅、小玉 聡 |
| 老年病科担当医 | 亀山 祐美 |
| 院外顧問 | 谷口 豪 (国立精神・神経医療研究センター) |
| 院外顧問 | 高橋 美和子(放射線医学総合研究所) |
| 院外顧問 | 川合 謙介、國井 尚人(自治医科大学) |
治療方針
当院てんかんセンターは、小児から成人まで全年齢層のてんかん患者さんに対して投薬から外科治療まで、あらゆる選択肢の中から最適な治療を提供すべく、包括的なてんかん診療に取り組んでいます。外科治療の対象となる患者さんについては、定期的に開催されるてんかんセンター症例検討会で診断や手術適応、手術法に関する詳細な検討を行います。
得意分野
- EMU (Epilepsy Monitoring Unit) 検査入院:てんかんであるか否か、どのような発作型なのかを判断するために有用な長時間ビデオ脳波検査を行います。さらに画像検査および神経心理検査も施行して、様々な面から患者さんの発作症状および合併する様々な問題を評価します。てんかんの鑑別診断として重要な、心因性非てんかん性発作の診断・治療も行っています。
- 外科治療では、病巣切除術、焦点切除術、軟膜化皮質多切術、脳葉切除・離断術、選択的海馬扁桃体切除術、海馬多切術、頭蓋内電極を用いた根治術、脳梁離断術、半球離断術、迷走神経刺激装置植込術・交換術の全術式に対応しています。
- SPECT、PETデータにもとづく焦点診断・機能評価
- 脳波、脳磁図の同時計測による診断精度の向上
対象疾患
全年齢層のてんかん,および,てんかん類似の症状を有する患者さん
先進・特殊医療
- 海馬多切術
- 最新の脳機能マッピング技術を用いた機能温存手術
- 頭蓋内電極を用いた真の難治てんかんの根治手術
- 迷走神経刺激療法
主な検査と説明
てんかんの診断・治療に必要な検査は多岐に渡ります。これらを必要に応じて組み合わせることで正確な診断・治療が可能となります。下記の検査はすべて当院で行うことが可能です。
- 脳波
てんかんの診断に必須の検査です。約1時間の検査です。 - MRI(~3T)
てんかんの原因となる画像上の異常を調べます。約30分の検査です。 - 脳磁図(MEG)
脳波では捕えられない異常波を捕えることができ、てんかん焦点診断に役立ちます。約2時間の検査です。 - 神経心理検査
てんかんに付随する認知機能の変容を評価することができます。複数の検査があり、それぞれ1-2時間の検査です。 - FDG-PET、脳血流SPECT、IMZ-SPECT
放射性医薬品を使って、脳糖代謝、脳血流、受容体密度分布を画像化します。てんかん焦点診断・機能評価に役立ちます。 - 発作時脳波(長時間ビデオ脳波)
発作時のビデオ脳波を記録します。原則として入院して行います。 - 発作時脳血流SPECTおよびSISCOM解析
発作時の脳血流変化を計測し、統計解析することでてんかん焦点を絞り込みます。 - 機能MRI
言語優位半球を非侵襲的に調べることができます。手術方針の決定に役立ちます。 - トラクトグラフィー
MRIによって脳深部の線維連絡を視覚化できます。手術方針の決定に役立ちます。 - 光トポグラフィー(NIRS)
てんかん焦点診断や言語優位半球の同定に役立ちます。約1時間の検査です。 - 和田テスト
カテーテル検査によって言語優位半球を確定させます。機能MRIで代用できる場合がほとんどです。 - 頭蓋内電極による焦点診断・脳機能マッピング
上記の検査をすべて行っても焦点の絞り込みが十分でない場合に、根治手術を目的として行います。
センター長